古物営業法とは
古物商許可を申請するにあたって、ついついその手続きばかりに目が行きがちです。なぜ許可制を採用しているのか、古物営業法を読み込めば、細かい規定を覚えずとも自然とどうすべきかを理解することができます。
古物営業法の目的(第1条)
まずは法律の目的についてです。多くの法律と同様、古物営業法の第1条に目的条文が記載されています。以下第1条の条文です。
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物営業法第1条
なぜ古物の売買について規制等を行っているのか。それは盗品等の売買の防止・速やかな発見等を図るためだったのです。よって次のようなモノを販売しようとするにあたって古物商許可が必要かどうかは一目瞭然だと思います。
- 自分で使っていたモノ
- 無償で譲り受けたモノ
- お客さんに売ったモノを買い戻して売却
- 外国で直接買い付けたモノ
お気づきの通り、全て古物商許可が不要です。いずれも盗品の可能性のあるモノを買い付けることがありません。
古物営業法の構成
古物営業法は39条から成る比較的条数の少ない法律です。構成は以下の通りとなっています。
古物営業法の構成
- 第一章 総則 (1・2条)
- 第二章 古物営業法の許可等
- 古物商及び古物市場主 (3~10条)
- 古物競りあっせん業者 (10条の2)
- 第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等 (11~21条)
- 第三章の二 古物競りあっせん業者の遵守事項等 (21条の2~21条の7)
- 第四章 監督 (22~25条)
- 第五章 雑則 (26~30条)
- 第六章 罰則 (31~39条)
以下詳しく確認していきます。
第一章 総則 (1・2条)
第1条はすでにご説明の通りです。第2条では以下の各定義が明記されています。
- 第2条1項 古物とは
- 第2条2項 古物営業とは
- 第2条3項 古物商とは
- 第2条4項 古物市場主とは
- 第2条5項 古物競りあっせん業者とは
ここでは古物の定義のみご説明します。第2条において古物の定義は以下の通りです。
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物営業法第2条1項
定義についてはそれぞれ別の記事をご用意しておりますのでご参照下さい。
第二章 古物営業法の許可等 (3~10条)
この章が古物営業法のメインの章であり、古物許可申請手続きのほとんどがこの条文を法律根拠としています。
- 第3条(許可)
- 第4条(許可の基準)
- 第5条(許可の手続及び許可証)
- 第6条(許可の取り消し)
- 第7条(変更の届出)
- 第8条(許可証の返納等)
- 第8条の2(閲覧等)
- 第9条(名義貸しの禁止)
- 第10条(競り売りの届出)
第3条では「 古物商及び古物市場主は都道府県公安委員会の許可を得なければならない 」 とされており、第4条では11項目に及ぶ許可を与えてはいけない者が列挙されています。そして第5条において古物商許可申請に関する手続き等の詳細が記載されています。
古物商許可を申請するにあたってはこの章で列挙される内容をよく理解した上で、管轄警察署の窓口とやり取りをする必要がございます。
第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等 (11~21条)
第三章では許可を得た古物商及び古物市場主の遵守事項等について記載があります。11~21条は以下の通りです。※第三章の二については割愛します。
- 第11条(許可証等の携帯)
- 第12条(標識の掲示等)
- 第13条(管理者)
- 第14条(営業の制限)
- 第15条(確認等及び申告)
- 第16条(帳簿等への記載等)
- 第17条(見出しなし)
- 第18条(見出しなし)
- 第19条(品触れ)
- 第20条(盗品及び遺失物の回復)
- 第21条(差し止め)
古物商許可を受けると営業がスタートしますが、この章を読むと営業するにあたっての遵守事項等が分かります。なお古物商を営むにあたって特に注意すべき条文があります。第20条です。
古物商が買い受け、又は交換した古物(指図証券、記名式所持人払証券(民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百二十条の十三に規定する記名式所持人払証券をいう。)及び無記名証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。
古物営業法第20条
古物商が盗品を買い取ってしまい、被害者又は遺失主から盗品の返却を求められたら無償で返還しなければならないという条文です。古物商にはとても厳しい条文です。ただし盗品が簡単に世の中に流通しないように古物の許可制を採用しています。当然と言えば当然でしょう。
盗品の買い取りと返却義務については別の記事で詳しく解説しますが、いずれにしても盗品の買取については細心の注意が必要となります。
第四章 監督(22~25条)
この章では警察職員や各都道府県公安委員会が古物商に対して行使できる権限について記載されています。条文は以下の通りです。
- 第22条(立入り及び調査)
- 第23条(指示)
- 第24条(営業の停止等)
- 第25条(聴聞の特例)
第五章 雑則 (26~30条)
雑則については以下の通りです。第四章に引き続き公安委員会ができることが記載されています。
- 第26条(情報の提供)
- 第27条(国家公安委員会への報告等)
- 第28条(権限の委任)
- 第29条(経過措置)
- 第30条(国家公安委員会規則への委任)
第六章 罰則(31~39条)
この章では古物営業法の各条文に違反した者に対する罰則について記載があります。三年以下の懲役又は百万円以下の罰金までの罰則がございます。
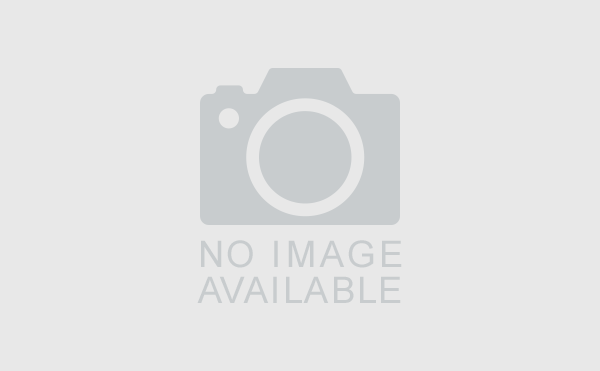
こんにちは、これはコメントです。
コメントの承認、編集、削除を始めるにはダッシュボードの「コメント」画面にアクセスしてください。
コメントのアバターは「Gravatar」から取得されます。