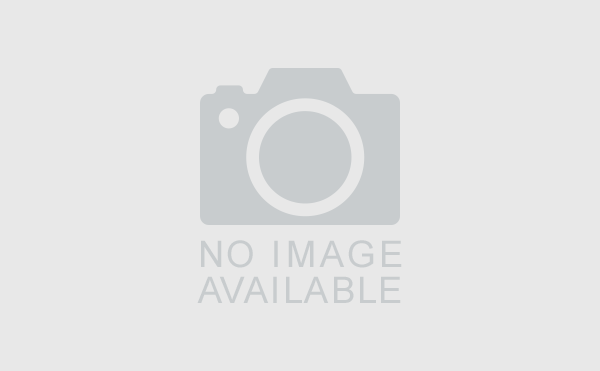古物商許可の欠格要件
許可の基準
古物営業法において、公安委員会は一定の事項に該当する者に許可を与えてはならないと規定しています。以下古物営業法の条文です。
公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
古物営業法第4条
一、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二、禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
五、住居の定まらない者
六、第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七、第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八、心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
九、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十一、法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
自己破産の手続きは破産手続開始決定の後、同時廃止・管財事件いずれかの手続きに進み、最終的に裁判所より免責許可決定によって債務が免除されます。この免責許可決定が下りるまでは、「破産者」として一部の職業に就けなくなる資格制限の状態にあり、復権を得ない者として扱われます。つまり免責許可決定が下りればこの条項に該当しませんので、古物商許可申請をしても問題ありません。自己破産経験者でも大丈夫です。
2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
禁固以上の刑
刑罰の種類は、科料<罰金刑<拘留<禁固刑<懲役刑<死刑 の6種類です。よって禁固刑以上とは「 禁固刑・懲役刑 」を指します。※なお罰金には過料というものもありますが、こちらは行政上の秩序罰で前科は付きません。
第三十一条に規定する罪
第31条は以下の通りです。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
古物営業法第31条
一、第三条(許可)の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号(古物商)又は第二号(古物市場主)に掲げる営業を営んだ者
二、偽りその他不正の手段により第三条(許可)の規定による許可を受けた者
三、第九条(名義貸しの禁止)の規定に違反した者
四、第二十四条(営業の停止等)の規定による公安委員会の命令に違反した者
要するに古物営業法でもっとも思い罰則(三年以下の懲役又は百万円以下の罰金)に処せられた者を指します。
刑法の一部に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられた
条項に記載の刑法は以下の通りです。
- 第235条(窃盗)
- 第247条(背任)
- 第254条(遺失物等横領)
- 第256条第2項(盗品譲受等)
古物営業法は盗品の売買の防止を目的としていますから、このような犯罪を犯した者に古物商許可を下すのは法の趣旨からも逸脱しているため適用されています。
3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
条項に記載の法律条文は以下の通りです。
- 第12条(「第10条暴力的要求行為の要求等の禁止」に違反したもので、反復して違反するおそれがある者への措置)
- 第12条の6(準暴力的要求行為に対する措置)
暴力団員との接触があり、暴力団員に暴力的要求行為を依頼した場合には、古物商許可が下りない可能性がございます。
5. 住居の定まらない者
住民票の住所と所在が一致していない場合は注意が必要です。
6. 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
第24条第1項は以下の通りです。
古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
古物営業法第24条1項
古物営業法に違反したことなどを理由に許可が取り消された場合は、その取り消しから5年間は古物商許可を得ることができません。
7. 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
前号の取り消し回避を目的として、古物商許可取り消し(もしくは当該取り消しをしないこと)の決定前に許可返納した者も、返納から5年間は古物商許可を得ることができません。
8. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
成年被後見人・被保佐人などは単独での法律行為ができないため、古物商許可を含む各許可制の業務について、そのほとんどを欠格とみなされてきました。しかし令和元年に「成年被後見人等の権利の制度に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(整備法)」が施行され、成年被後見人等であっても、個別的・実質的な審査によって適正を見極めるよう、この条文が追加されました。
9. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
未成年は古物商許可を得ることができません。ただし婚姻している未成年の場合は成年者とみなされますので許可申請が可能です。
10. 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
営業所には、業務の適正な実施のための責任者として管理者を常駐させる必要がございます。そして当然ながらその管理者は取り扱いの古物について一定の知識や経験を有している者が必要なケースもございます。
11. 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
法人の役員も上記1~8号まで該当してはなりません。