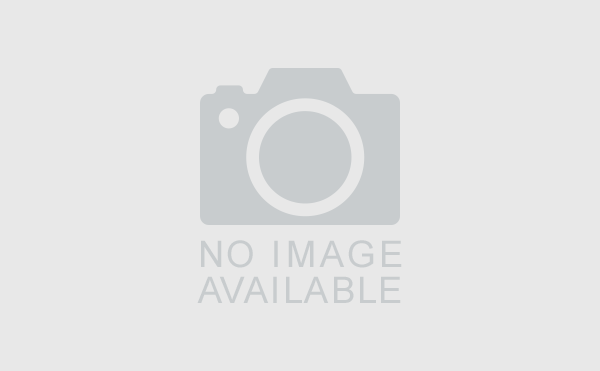行商とは
行商とは
結論:「 行商をする 」を必ず選択
古物商許可申請書には「行商をする・しない」という選択項目がございます。まず結論から申し上げますと「行商をする」を選択して下さい。メリットはあれどデメリットはありません。また審査が難しくなるということもありません。
行商の定義
行商とは「 古物商が自らの営業所以外の場所で行う古物の取引 」のことを言います。そもそも古物商には以下の通り営業の制限がございます。
古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。
古物営業法第14条1項
古物商は以下の場所以外で古物営業をしてはならない(※古物商を除く)と規定されています。
- 自らの営業所
- 相手方の住所若しくは居所
しかし実際の現場では、この2箇所以外にも古物営業を行うことはございます。
仮設店舗での古物営業
しかし、この条文のただし書きで制限緩和がなされています。
ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。
2、前項ただし書に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項ただし書の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。
古物営業法第14条1項但し書き・2項
とあります。いわゆる催事場などのことを指します。仮設店舗において古物営業を行う場合には、古物商許可申請において「 行商する 」と記載し、その場所を管轄する公安委員会に「 仮設店舗営業届出 」を提出する必要がございます。(その管轄に営業所がない場合は、自らの営業所を管轄する警察署経由で提出することができます。)
いずれにしても自らの営業所以外で古物営業を行いたいのであれば、すなわちそれは「 行商をする 」ことを意味します。
古物市場での取引
古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。
古物営業法第14条3項
自らの営業所以外の取引場所として、古物市場がございます。これはいわゆるプロ同士の取引場で、主に仕入の場所として利用されます。古物市場での取引を希望される場合も「 行商をする 」を申請しなければなりません。
行商従業者証
行商をする際には以下の通りの規定がございます。
古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
古物営業法第11条
2、古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
3、古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
行商をする際は 「 許可証 」+「 行商従業者証 」(従業員に行商をさせる場合)が必要です。また相手方から掲示を求められたら応じなければなりません。この「 行商従業者証 」は自ら作成する必要がございます。